「おい足」
「あっ踏んだ? ごめん!」
「そうじゃねぇ。お前足、血出てるぞ」
「あっ、あぁこれね。ちょっと靴擦れしちゃって」
「…ちゃんと手当てしとけよ」
「はいはーい」
「………んな真新しい靴であれだけ走りゃそうなるだろ」
医務室に向かう後ろ姿に、呟いた。
昼間、島でルフィを追って走るナミを見かけた。今日の船長のお目付役はナミだった。島に降りる前、「かわいいでしょ?」と俺に見せてきたあのサンダルは、今日おろしたばかりのものだ。口では文句を言いつつも、律儀にあの麦わら帽子を追う顔はいつでも満足気だ。
相手がルフィ以外なら、ナミがあの靴で走り回ることはなかっただろう。例えその相手が俺で、今日のルフィと同じように振る舞っても、きっとあんなふうに走り回ったりはしない。それはナミ自身が望むように動いた結果なのだと思う。
いつだって、ナミを一番に動かすのはあの麦わら帽子の船長で。ナミと関係を持った今だってその優先順位は変わらない。同じ船に乗るものとして、それは至極当然の事で、そうあるべきだとすら思う。それでもナミが船長のために動く度、くだらない嫉妬心が猛火のように燃え上がるのを、未だに俺は抑えられない。
比べるもんじゃないこともよく分かっている。ナミに限らずこの船に乗る者全員が、船長第一で動いている。だからナミの今日の行動も当たり前のことなのだ。頭では、分かっている。だが目の前を通り過ぎたナミの、めくれたかかとの皮膚が、滲んだ深紅の傷痕が、俺とルフィとの差を鮮明に表していて気分が悪かった。
夜、飯を食い終えた俺は早々にダイニングを出て、甲板で一人酒を飲んでいた。昼間見た小さな傷痕が脳裏にチラついて、どうにか飲み込んだはずの嫉妬心が消化不良を起こしていた。こういう時は一人で淡々と時間を消費したいのに、しかし勘の良いうちの航海士はそれを許してはくれなかった。
「ゾーロ。どうしたの? 調子悪い?」
「いや」
「ふーん」
隣いい? と言いながらすでに隣に腰を下ろしたナミのかかとには、きれいに絆創膏が貼られていた。持ってきた酒瓶の栓をポンと開けて、ナミはこくこくと喉を鳴らしながら瓶の三分の一ほどを一気に飲み干した。酒が通るごとに上下する、その透けるように白い喉に噛み付いてしまい。そこからナミの全てを喰らい尽くしたら、今度こそお前は俺のものになってくれるのだろうか。
俺の視線に気づいたナミがこちらを向いて口を開いた。
「妬いてるの?」
立てた膝の上にちょんと頭を乗せて、こちらを覗き込む。こういうあざとさは嫌いじゃないが、今は素直に乗ってやれる気分ではなかった。
「別に。そんなんじゃねぇよ」
努めて無感情に返事をした。一度気持ちを表に出したら、止まらなくなりそうだった。しばらく俺の顔をじっと見ていたナミだったが、ふっと短くため息をついて前を向き直した。
「そ。一つ言うけど、私は妬いてるわよ、2年前からずっと」
「あ? どういう意味だ?」
「んー…分かんないか。あんたたち二人とも無自覚だもんねぇ」
ふふっ、と笑ってまた酒瓶に口を付けた。意味がわからず答えを求めた俺の視線を無視して、ナミは瓶を左右に振って酒の残量を確認している。もう一本持ってくれば良かった、と独りごちた後、諦めたようにさっきの続きの話をし始めた。
「あんたはさぁ。出会った時からずっと、ルフィ第一なのよ。私が入る隙間なんかないくらい、あんたたちはお互いを強く思ってる。友情とか、愛情とか、そんな名前がつけられるほど安っぽい繋がりじゃなくてさ。わかる?」
「……」
「船長の右腕、だとか、ルフィの一番最初の仲間、とか。肩書きはいろいろあると思うんだけどね。その関係性は簡単に言葉にはできないし、他の何者も立ち入れないの」
「それを言うならお前とルフィだって、そうだろ?」
「…あんたから見れば、そうなのかな。船長と航海士って立場的なものもあるしね。それじゃ、お互いにそう思ってるのかもしれない。お互いにルフィとの関係に、特別さを感じてるのよね。
…あのね、これは私の感じ方なんだけどね、」
そう言いながらナミは、俺の手にしっとりと柔らかな手を重ねた。
「私たちは、海賊じゃない? 奪って、奪われて、争って、傷つけて…そういう中に身を置いていて、奪ってやりたいとか、張り合いたいとか、そんな気が起きないのよ。あんたたちのその深い繋がりに対してはね。
それは、あんたに抱かれてからもずっと変わらない。あんたたちの関係も、何も変わってない。きっとそれが船の中でのあるべき関係性なの。それはよく分かってるの。分かってるんだけどさ…そういう関係性って、多分私とゾロとの間では成立しなくて。
なんだろうね、絶対切れることがない、絶対的な信頼の上に成り立っている、すごく…尊い繋がりなんだよね、あんたとルフィの繋がりは。
それがやっぱり羨ましいし、あんたを独占できないのは少しだけ悔しいから…ずっと妬いてるわ」
重ねた手をすりすりと撫でながら、子どもに言い聞かせるように優しく穏やかに、ナミは話した。
「私は好きよ。あんたも、ルフィも。どっちも大切だし、守りたいし、あんたたちになら守られたい。こういう人同士の繋がりをさ、秤にかけること自体が間違ってるんだと思うわ」
「ナミ、俺は…」
「ううん、何も言わなくていい。今から出てくる言葉には、きっと少しずつ嘘が入っちゃう。私が先にここまで話して、気を遣わないわけないもの。あんたに嘘つかせたくないの。そういうのは嫌いでしょ?」
「ナミ……」
「好きよ、ゾロ」
祈るように目を閉じて呟いたナミは、重ねた手につるりとした額を当てて、小さく微笑んだ。ナミの言う”好き”が一体どういう類の好きであるのか、俺にはもうよくわからなかった。
ただ一つ言えることは、俺はやっぱりナミが好きで、ナミも少なからず俺を好いてくれているということだった。
俺たちが海賊でなければ。
どこかの島で出会った、ただの男と女だったなら。
そしたらきっと、今のような関係を築けてはいなかったのだろう。この苦しさや痛みが、隣にいることの代償なのだと思う。俺たちの間には船長が必要で、その両脇に立つのが俺たちだ。
ナミの言う通りなのかもしれない。
船長を挟んだ俺たちの関係性のそれぞれの重さを、秤にかけることに意味はない。それは全く性質の異なるものであるし、今この瞬間、ナミの隣にいるのは俺だ。それでもう十分じゃないか。
頭では分かっているのに、互いの船長への想いの大きさに嫉妬せずにはいられないなんて。
なんと不毛な片思いなのだろう。かわいそうだな、俺も、ナミも。
「好きよ、ゾロ」
「…俺もだ、ナミ」
「ふふっ、へんよね。最初はさ、ゾロが私を見ているって、それだけですごく嬉しかったの。好きだって言われるたびに胸がドキドキして。人を好きになることって、こんなに幸福なことなんだって思ってたのに。
いつのまにか、その状態が当たり前になって、もっともっと、って。あんたの一番になりたくなっちゃったの。私だけを見ていて欲しくなっちゃったの。…欲張りよね。欲深い女は、嫌かしら」
「いや……大好きだ」
「ありがとう、ゾロ」
顔を上げたナミは重ねた手をそっと離して、その手を俺の頬に添わせた。俺に向き合ったナミは、笑っていた。ふわりと柔らかな、慈愛に満ちた笑みだった。
「ね、キスしよっか」
思いついたばかりの新しい遊びに誘うような、無邪気な響きだった。だから交わすキスも遊ぶような、軽く弾むキスだった。今まで交わしたどの口づけよりも、軽くて、何の意味もない。
もう今までのようにナミと触れ合うことは出来ないのかもしれない。遊びのように冗談めかしていなければ、触れることさえも出来ないのかもしれない。
海賊であること、夢を叶えること、船長の隣に立つこと。その意味を、今さらながら思い知った。
「私たち、これからどうしようか」
「…どうするって?」
「今までみたいに、何にも気にしてないフリしてキスしたりセックスしたり、出来る?」
「できねぇ、かもな」
「触れ合うたびに辛くなるような気がするのよね。このままだと」
「……触れることだけが、気持ちを表す術ではないだろ」
「……そっか」
そうかもね、と俯きながら笑みを作った、その横顔は寂しげだった。
「ねぇ、好きよ」
「あぁ。俺もだ」
「それで、十分よね」
俺を見ずに静かに呟いたその言葉は、まるでナミ自身に言い聞かせるための言葉のようだった。
「ナミお前…終わらせようとしてるのか?」
「ん……」
「ルフィが俺たちの一番じゃ、俺たち二人の関係は保てないのか?」
「……だって…さっきので分かったでしょ? 今までみたいにはもう出来ないよ。ろくにキスもセックスも出来ないのに、それなのにゾロを縛り付けておくことなんて…」
「勝手に決めんな。さっきから一方的にお前一人で決めつけて、俺の気持ちはどうなる? お前を抱けねぇからなんだ。お前は俺の欲の捌け口に成り下がってたのか? 違うだろうが。俺の気持ちは、お前には届いてなかったか?」
やっと俺の方を見た、ナミの瞳は揺れていた。
俺が気付くよりずっと前から、俺とルフィとの繋がりの強さを感じて、それでも何も言わずに俺の隣にいてくれたナミは一体どんな気持ちだったのだろう。今まで俺が感じてきた嫉妬など、ナミが抱えてきた苦しさと比べたら、ほんのわずかなものなのかもしれない。そう思うとたまらなくなり、俺はナミの身体を抱き寄せてそっと腕の中に閉じ込めた。
「ごめん」
「ゾロ…」
ごめんナミ、ごめん、と何度も繰り返した。
気付かなくてごめん。
傷つけてごめん。
苦しめてごめん。
好きになって、ごめん。
「ナミ、俺はな。お前が好きで、好きすぎて、離れた方がお前は楽になれるかもしれねぇのに、放してやることができねぇ。お前にここまで言わせておいて、それでもまだ未練がましく、お前と一緒にいたいと思っちまってる。
なぁナミ。今までみたいにいかねぇこともあると思う。それを辛く思うこともあるかもしれねぇ。けど、そういうのを一つずつ、また一からお前と始めたい。それじゃあダメか?」
「………」
「……ナミ?」
俺の問いに対してなかなか言葉を発しないナミの反応が気になって、そっと顔を覗き込んだ。俯いているせいでその表情は影になりよく見えないが、その目からはぽたり、ぽたりと涙がこぼれ落ちていた。
「……ぁたしだって、こんなに好きなのに…うぅっ……離れたいわけ、ないじゃないっ」
絞り出すようなその言葉を聞いて、ナミの身体を力一杯抱きしめた。
「放さねぇ…放せねぇから、ずっとここにいろよナミ。俺のそばにいろ」
「うん……うん」
苦しかった。
ナミの涙まじりの声が。小刻みに震える身体が。ナミをそうさせるのが俺自身であることが。
これ以上の言葉を交わすことなく、俺とナミはただ抱き合って一晩を過ごした。
明け方、空に明るさが戻りそろそろコックが起き出すという頃になって、ようやくナミを解放した。二人ともろくに眠りもせずに夜を過ごした割に、どこかスッキリとした顔をしていた。
「ん〜…もう朝になっちゃったね。部屋戻ろっか、すぐ朝ご飯の時間だけど」
「そうだな。クソコックに見つかっても面倒だ」
「サンジくん起きる頃だもんね」
そう言って立ち上がったナミは、うーん、と大きく伸びをしてゆっくりと歩き出した。ふと、この光景に既視感を覚えた。これは……。
「なぁナミ、覚えてるか?」
「んー、何を?」
「俺たちが最初にキスした時」
「あぁ。覚えてる。忘れるわけないじゃない」
ナミはクスリと笑って、懐かしいものでも見るように目を細めながら俺を見つめた。
「こんな朝だったよね。初めてのキス」
「あぁ」
そう。あれは初めてナミを抱いた夜が明けた、まっさらな朝だった。
俺たちの始まりは少々歪だった。
二人で酒を飲んでいた月のきれいな夜だった。ほとんどの酒が空になり、口にするものがなくなったとき、一瞬、ばちんと目が合った。そこから「好きだ」も「愛してる」も、唇を触れ合わせることもなく、どちらともなく手を伸ばして肌に触れたが最後、ただ貪るように衝動的に身体を繋げた。言葉一つも交わさぬまま、ただひたすらナミを抱いた。こんなにもしっくりくる女は初めてで、夢中で、何度も、何度も抱いた。抱きながら、『あぁ、俺はナミが好きだったのか』と、これまで名前をつけてこなかったナミに対する気持ちをようやく認めることができたのだった。
朝方まで続いたそれを終えた時、薄く光が射し込む中で、言葉を発したのは俺の方だった。
『ナミ、好きだ』
薄い毛布に包まったナミの落ちかけたまぶたが、一瞬にしてパッと開いた。
『今、好きって言った?』
『あぁ、言った』
『好きなの?』
『好きだ。そう言っただろ』
『え、私てっきり…』
『遊びと思ったか?』
『……うん』
『何も言わずに抱いたらそりゃそう思うか。悪かった。俺はお前が好きだから、抱いた。お前も、俺が好きだろ?』
『っ! じ、自信過剰! なんでそう言えるのよ』
『昨日、目が合っただろ。あれで分かった、俺もお前も同じだって。だから手を出した』
『‥‥ムカつく』
『でも当たりだろ?』
『だからムカつくの!』
頬を染めながらしかめっ面を作るナミが、心底可愛かった。ナミの膨らんだ頬に軽く手を添えて、こちらを向かせてキスをした。
『順番、めちゃくちゃね』
『そうだな、悪い』
顔を見合わせて声を出して笑った。
幸せな朝だった。
「ナミ、」
「ん?」
俺の顔を見上げたナミの頬に手を添えて、乾いてしまった唇に、そっと唇を合わせた。
「好きだ、ナミ」
「ゾロ…」
「やり直そう。こうやって一つずつ、新しくしていこう」
「……やってみよっか」
にこりと笑ったナミの背景に、紫煙を燻らせる金髪が見えた。
「おうおう、朝から熱いな」
「サンジくん! おはよう」
「おはようナミさん」
「何覗き見してんだよ、エロガッパ」
「あぁ? こんな見晴らしの良い場所でナミさんに手ぇ出してる方が悪いだろ」
「ねぇ〜。朝から盛られちゃ参っちゃうわ」
「おいナミてめぇ、お前はこっち側だろうが」
「なーによ、共犯だとでも言いたいの?」
「共犯だろどう見ても」
「はいそこまで〜。こんな清々しい朝にイライラしちゃもったいねぇ。キッチンで温かいお茶でもいかがです? レディ」
「いただくわ、サンジくん」
「おい俺にもよこせ、エロコック」
「俺はレディにお茶を淹れて差し上げるんだよ。テメェで注げマリモ野郎」
「残念だったわね」
こちらを向いてべっ、と小さく舌を出したナミは、もうすっかりいつもの航海士の顔だった。
こうやって新しい俺たちも、また日常に溶け込んでいく。
終

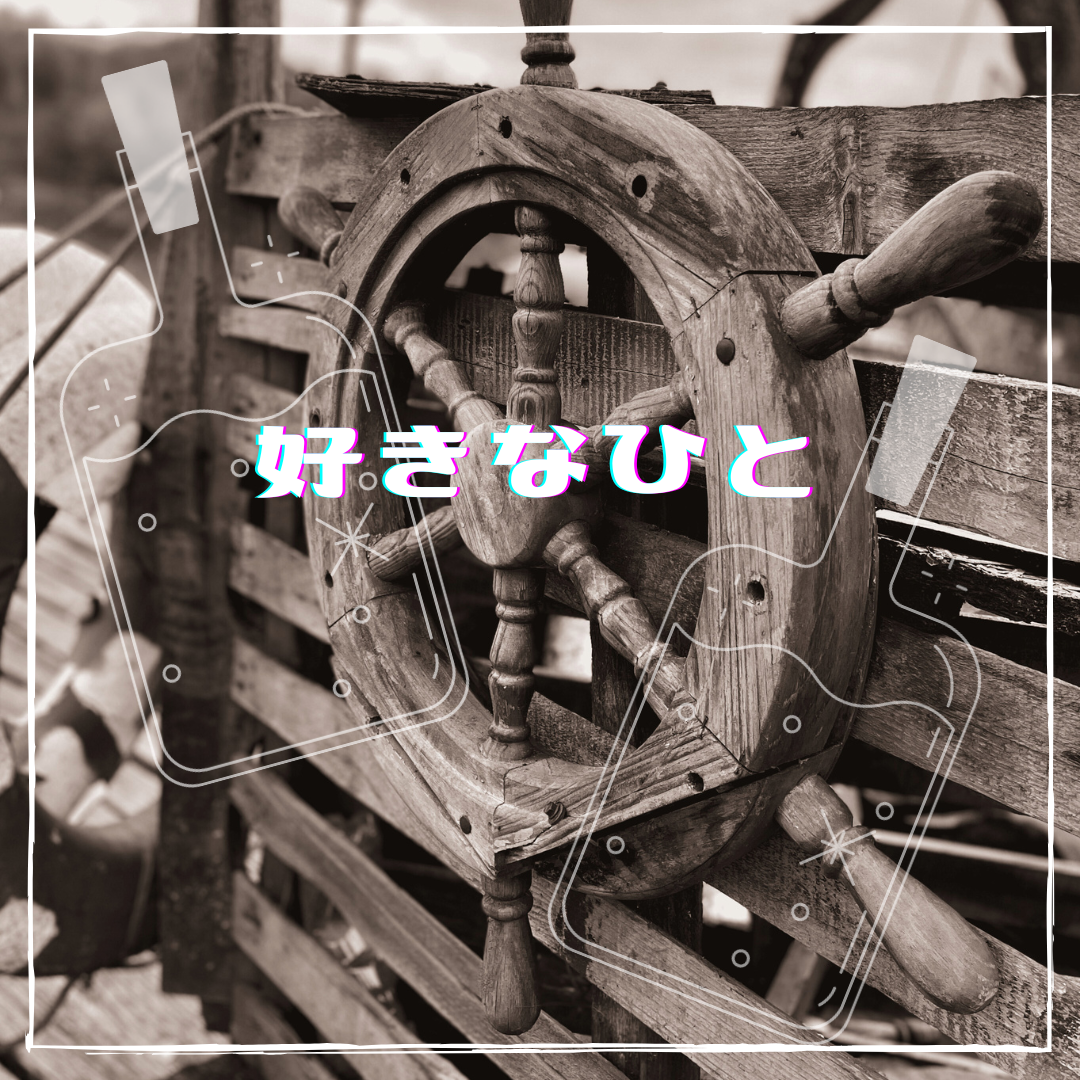


コメント