「私たち、いつまでこんなことしてられるのかしらね」
乾杯の後にジョッキを半分ほど空けると、ナミはぽそりとつぶやいた。
「こんなこと?」
「週末、昼間から飲み歩いて。話すことも特になくて。それも毎週末よ? 相手のいない男女が集って。不健全じゃない?」
不健全。
何をもって健全とするのか、ゾロにはよく分からなかった。返事をする代わりに大ジョッキの底に2cmほど溜まったビールを勢いよく流し込むと、その味は心なしか一口目よりも幾分苦味を増した気がした。
「ビール?」
「ん、あぁ」
「すみませーん」
店員を呼んでジョッキを干したナミの白い喉を見つめて、もう一度、さっきの言葉を噛み締めてみる。
毎週末。特に話すこともない、恋人同士でもない男女が、昼間から飲み歩く。
その現象が不健全というのなら、ここ2年の自分たちの週末はほとんど不健全だっただろう。
学生時代の延長で、就職後もほぼ毎週末、どこかしらで集まって酒を飲んでバカな話をして。それが3年もすれば、仕事の都合だ結婚だと一人、またひとり集まりが悪くなり、気付けば卒後6年目にはゾロとナミの二人だけが、毎週末のレギュラーメンバーになっていた。
「まさか30になってもこんなやって週末あんたと飲み歩いてるとは思わなかったわ」
運ばれてきた大ジョッキをそれぞれのコースターの上に置き、ナミは苦笑しながらそれを両手で持ち上げ口を付けた。
「20代の延長の30代ならまぁ、こんなもんだろ」
こんもりと乗ったきめ細かい泡を口に含んで、後から押し寄せる苦い微炭酸を、喉を鳴らして流し込む。
自分達の週末の集いは、このジョッキのビールみたいなものだとゾロは思う。特別好きだから、ではなくて、それが当たり前だから。乾杯にほしいのも、飽きずに飲めるのも、酔いをもたらしてくれるのも、このビールがちょうど良くて。その相手はもうナミ以外、考えられなくなっている。
「後悔してんのか?」
「なにを?」
「いただろ、結婚しそうだった男」
ゾロの記憶の片隅にうっすらと残る、爽やかな笑顔の男。学生の頃ナミと同じゼミに所属していた、やたら愛想の良い、いかにもいい奴なその男。卒業後、結婚するかも、という話が出たのは仲間内ではナミが最初で、しかしその3ヶ月後にはその男とは縁が切れていた。
「うーん、そんなこともあったっけね」
「それを嘆いてるわけじゃねえのか」
「嘆くわけないでしょ。あの時じゃなかったし、私にはアイツじゃなかったのよ」
じゃあなにをそんなに悲観するのか、この飲み会のなにが不満なのか、いよいよ分からなくなってくる。目ざとくその表情を読み取ると、ナミはふぅ、とひとつ息を吐き出して口を開いた。
「別にね、不満とかじゃないの。あんたと飲むの気が楽だし。なんでも飲めるから行きたいお店連れ回せるし。ちょうど良いのよ、すごく」
「いいじゃねぇかそれで。なにがまずい?」
「ちょうど良すぎて。たまにちょっと、不安になる」
両手で持ち上げたジョッキを傾けて含んだひと口が場違いに爽快で、ナミの口から笑いが漏れた。
「たまに考えるの。この先あんた以上に合う人も、あんた以上に気楽な人も現れないんじゃないかって。そうしたら私、あんたがいなくなっちゃった時に急に空っぽになって、きっとひどく絶望する」
「いなくなるってなんだ」
「あんたは私のじゃないもの。いい相手が見つかって、その人との時間を優先したくなった時、私はそれを邪魔したくないしそんな権利も持ってない。それがあんたのいなくなるとき」
そんなことを、考えもしなかった。こういう時間が、週末が、この先ずっと当たり前のように続いていくと、ゾロはどこかでそう思っていた。それがなくなると考えた時、たしかに自分の内側に空洞ができた気がした。ナミの不安の正体はおそらくこれと同じものだ。
ちょうど運ばれてきた漬物と湯気を立てる厚焼きたまごがテーブルの上に並べられ、二人は反射的に割り箸を手に取る。左手にさらりとした紙の手触り。
「あっ」
「ん?」
箸を紙袋から取り出して皿の上に置くと、手に残ったその袋を1回、2回と細く折っていく。
「手ぇ出せ」
「手?」
差し出された両方の手のうち、向かって右側、ナミの左の手を手に取って軽く引き寄せる。
細く折った箸袋を、ナミの左の薬指にそっと巻きつけて、ほどけないように2回、結んだ。
「なにこれ、おみくじ?」
「なわけあるかよ。その指に輪っかつけたら、……そういう意味だろうが」
「……は? なに、本気?」
冗談ではないことは、ゾロの表情を見れば明らかだった。ぎゅっと結んだ唇も懇願するような瞳も、男の整った相貌を際立たせて、気恥ずかしさを覚えたナミは思わず目を伏せた。
「こんなんで、私が喜ぶとでも?」
「いや、これは俺のための救済措置」
救済、と呟いたナミの左の薬指を、ゾロの右手がそっとすくって親指で愛おしそうに撫でる。
「この先、お前にいなくなられちゃかなわねぇ。俺がお前のもんじゃねぇなら、お前が俺のになってくれよ」
撫でる指の動きが止まって、ゾロの両手がもう一度、解けかけた薬指の輪を結び直す。
「今はこれで、繋ぎ止められてくんねぇか?」
いつになく真剣な声の色が、ナミの胸の内を騒がせる。じわじわと広がっていくこれは、きっと戸惑いだけではなくて。
「私も憧れた時期はあったから、いろんなパターン想像したけど。これは考えたことなかったな」
視線の先、薬指に結び付いた縁がかわいらしくて愛しくて、どんなリングをもらうより今は一番嬉しいと思う。
「あんたがいなくならないなら、それでいい」
互いにこぼれる笑みに喜びと照れを感じつつ、持ち上げたジョッキを音を立てて合わせた。口を付けたビールの泡はすっかりへたってしまったけれど、安定のキレと苦味が喉を通り過ぎていく。
いつもの店で。いつもの酒を。いつもの二人で。
約束された週末のつづき、いつも通りの二人の指に、救済の証が結ばれる。
終



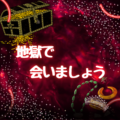
コメント